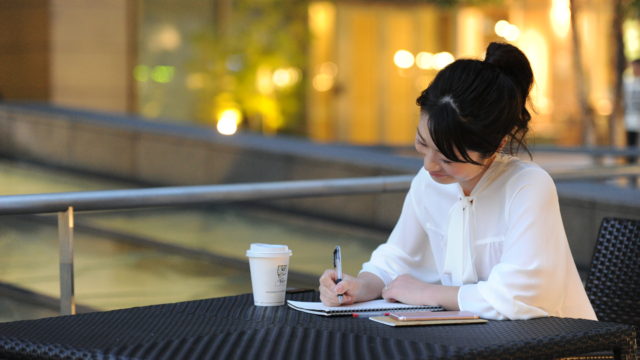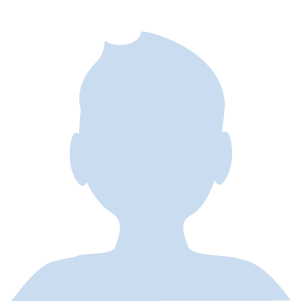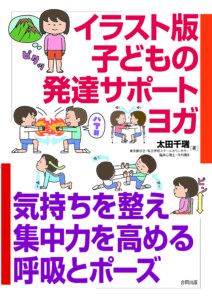ちず先生!教えて!シリーズ 第1弾
本日は、
発達障害の疑いがあるとされる3歳のあるAくんのお悩みを取り上げます。
保護者様の悩みポイントは、たった1つ
「ウンチを毎日投げて遊ばないで欲しい」
オムツの中を確認して、触ってしまうだけでなく、
ウンチをそこら中に巻き散らかしているとのこと
しかも、その飛び散ったウンチを8ヶ月の妹が食べてしまう・・・
毎日毎日そんなことが起きたら・・・
「誰か、助けて」と叫びたくなるでしょう

ウンチくん問題をどうするか?
トイレットトレーニングの時期において、
ウンチくん問題は複雑です。
まず、大切なのは、子どもにとってウンチは
自分のかけがえのない一部であること
使い古した愛着のあるオモチャであること
この2つの視点を持つことをここがけましょう
つい汚いもので、臭いもののため、早く処理したくなりますが、
子どもにとっては宝物の延長にあるのです
食べたものをきちんと自分の体で消化できている
そういう体の機能に感謝するための”宝物”ですね
※あたり構わずウンチをしてしまう遺糞症というのもありますが、
本記事では、ウンチあそびについて取り組んで欲しいことのみ
ご説明いたします。
このようなウンチ問題に取り組むために必要な観点は次の4点です
- ①トイレットトレーニングを粘る
- ②第2子がいない時間をスペシャルタイムにする
- ③タッチケアをする
- ④感覚統合あそびを取り入れる
トイレットトレーニングを粘る
第二子が産まれてようやく落ち着いたところに
上のお子さんのトイレットトレーニングの時期がやってきました
この時期は、本当にどちらのお子様に目を向けても
毎日が事件!ばかりで心も体もともに疲れてしまうでしょう
あっという間に来る食事と授乳の時間に
突然、ウンチタイムが来る・・・
なかなかタイミングを予測するのは難しいのですが、
それでも食事の後が多いとか、
外出後が多いなど、タイミングを予測するため、
1週間、ウンチタイムチェックを設けます。
「ウンチした!」、と思ったら携帯に日時をメモ
落ち着いてメモできるときに、その状況(食後など)の
タイミングを書いて残します
トイレになるべく連れていき、トイレですることを絵本や言葉で
何度も何度も何度も(!)話します。
「よくできたね!ウンチくん、さよなら〜!」と
できてもできなくても、トイレの中までいけなかったら
トイレ前の廊下でも良いので、場所を必ず変えて、
ママの笑顔+さようならタイムを設けます。
(笑顔は作り笑いで十分でしょう!!)
そのあとに、ママからお子様へ”がんばった証”として、プレゼントをあげましょう。
プレゼントは、お菓子やハグではなく、
風船スクイーズです。
<風船スクイーズの作り方>
・小さいサイズの風船を用意する
・水と小麦を混ぜて泥状にする
・風船の中に入れる
詳細はこちらから 風船でつくるスクイーズ
この風船スクイーズを両手に持たせ、握らせて、
「Aちゃん、よくできました!」と大げさにリアクションしましょう
その後、数分スクイーズで遊ばせたら、取り上げます。
行動の切り替えをなるべく明確にして、
別のおもちゃ(ぬいぐるみやミニカー)へ誘導して、
遊びの時間を続けていくようにします。
落ち着いたら、おんぶしていた第二子にたっぷりの愛情を込めて
抱っこしたり、オムツを替えたりしましょう。
とってもつらいですが、第二子が泣いていても、1日のうち、
ウンチタイムだけでも第一子を優先しましょう。
家族がいたら、ぜひその間、第二子の様子をみてもらいましょう。
(ここでパパがおむつ換えやミルクしてくれたらいいですね!希望ですが)

第2子がいない時間をスペシャルタイムにする
おそらくですが、Aちゃんは、妹Bちゃんと楽しく遊びたいという
気持ちと、ママに遊んで欲しい・かまって欲しい気持ちが
織り混ざった状態で、ウンチを投げつけているように思います
妹Bちゃんがウンチを食べてしまう反応は、
もしかしたら、お菓子を半分分けて与えるようなイメージを持っているかもしれないのです。
ただAちゃんは、もしかしたら衝動性にウンチからの開放感を味わいたくて
そのウンチをBちゃんとのコミュニケーションツールにしてしまっているのかも
しれません。(あくまでも個人的予想です)
これを解決するには、仕上げ拭きを優しく行うことと、
「言葉と気持ちを一致させる経験」を
増やすことが大切です。
お子様が、無反応でも、リアクションはしてくれるものの、
無視されてしまっても、勝手に1人で遊んで動き回っていても、
諦めずに続けましょう。
具体的には、「電車、黄色いね」という具体物の説明にはじまり、
「電車、速いね〜」という具体物の機能の話題に触れ、
「電車、かっこいいね!」という具体物への感想(=気持ち)を
言語化するという流れから成り立ちます。
そして、「そっか、電車、ここに置きたかったのかな?」
「ママも電車乗りたいな」と、どんどん子どもの心の世界に入っていきましょう
Aちゃんの心の世界に入るためには、第二子であるBちゃんのお世話を
ストップすることにもなります。
ママは、世界一すばらしい存在だけど、ロボットではありません。
同時に全てはできなくて当たり前です。
とにかく、第一子と一緒の時間を週に1度、ふんばって作りましょう。
家族・親戚・近所の方に頼れない場合には、
地域の相談センターやママ友に協力してもらっても良いかもしれません。
数ヶ月続く場合には、お子様の心理療法も選択肢に入れても良いでしょう。
タッチケアをしよう
タッチケアとは?
とっても簡単にいうと、親子のコミュニケーションの
1つの形です。
マッサージなど触れ方の基本を知ることで
関わり方の選択肢が増えるかもしれません。
サイトより保護者の方が購入して取り組むための資料も請求できます
どうぞ参考になさってください
タッチケアはこちらから
感覚統合あそびをしよう
Aちゃんの発達段階においては、感覚統合が未熟なため、
触覚から育てていくような遊びが有効だと考えます
具体的には、
・ボールプールに連れていく(自宅でも段ボールにビニールボールをたくさん入れるか、
柔らかいタオルをいっぱいにして代用することはできます)
・抱っこしてブランコに一緒に乗る
・絵の具でペインティング
・お風呂で石鹸の泡で遊ぶ
・冷たい⇆温かいがわかるように、水とお湯を交互にかけて、
「冷たいね、熱いね」と声をかける
・シーツブランコ:シーツに子どもをのせて、左右に揺らします
歌を歌いながら楽しい雰囲気で行ないます
安全に気をつけて、できることからはじめてみましょう
最後に
とても可愛い我が子。されど、子育てには教科書はなく、
予想したことはことごとく覆されるが子育て。
ママが、今取り組んでいることは、”失敗ではありません”
ぜひ、少しでもお子様の行動が落ち着かれることを祈って・・・
何かの参考になれば嬉しいです
個人情報保護のため、
お子様の年齢や性別など
多少の変更を加えております。
お問い合わせはこちらからもお受けしております

唯一無二の「自分」に出会う
一生懸命生きてきたはずなのに、ふと無力感に追われる・・
こんなになんで忙しいんだろう?と疑問に思う・・・
教育の現場で長く働いていると、そういう気持ちを持つ<先生>に出会うことがありました。
また、子育てに悩む保護者の方々が、”自分らしい人生”を送れていないことにも気づきました。
専門知識を深めて、仕事にも自分の人生を豊かにすることにもつながるための講座と相談をcandrika promovel では広げています。
臨床心理士・公認心理師・ヨガ講師(RYT500およびキッズヨガ 、MBSR、アンガーマジメントなど多数の研修資格を取得)の太田千瑞が自由自在に生き抜く方法を皆様へお届けします。